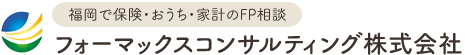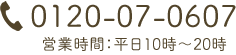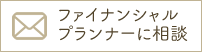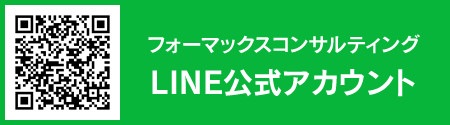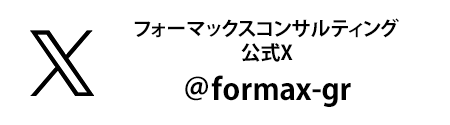生前贈与はどうやるの?生命保険の活用方法とは
生きているうちに財産を受け渡す「生前贈与」、あげたい人にあげたい財産を渡すことができるだけでなく、相続税の軽減というメリットもあります。
今回はそんな生前贈与の方法や、生命保険を活用した方法、メリットについて解説していきます!
生前贈与と相続の違い
「生前贈与」は、生きているうちに相手と贈与契約を結び、契約に基づいて財産の受け渡しを行うことです。贈与契約は、財産を無償で相手に渡す意志の表示と、相手がそれを承諾することで、双方の合意があることが条件ですが、渡す相手は配偶者や子ども、孫のほか、他人でも良いため、渡したい相手に財産を渡すことができます。
一方「相続」は、亡くなってから財産を法定相続人に受け渡すことです。
生前贈与は「贈与税」、相続は「相続税」の対象となり、それぞれ基礎控除額が異なります。
生前贈与のメリットとデメリット
メリット
・相続税の額を減らすことができる
・本人の意思で相手や渡す財産、渡す時期を決められる
・相続トラブルの防止につながる
デメリット
・成立させるための適切な手続きが必要
・贈与時期によっては相続税の対象となる
・贈与額によって贈与税がかかる
生前贈与の方法
生前贈与には2つの方法があり、併用や変更ができないためどちらかの方法を選ぶ必要があります。
①暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間を区切りとして贈与を行う方法です。年間110万円までは非課税となります。非課税枠を超えた額にかかる贈与税は、相手との関係により税率が異なります。

出典:マニュライフ生命「生前贈与のやり方は?自分でできる手続きの流れや生命保険の活用方法も解説」より
参照:国税庁 令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!
参照:国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)
参照:国税庁 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
②相続時精算課税制度
原則60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の孫や子どもに対して贈与した際に使える制度で、総額2,500万円までは非課税となります。受け取った財産の総額が2,500万円を超えた場合、贈与した人が亡くなった時にまとめて相続税として納税が必要です。ただし、年間110万円までは基礎控除に含まれるため、贈与総額には加算されません。
生命保険の活用方法
生前贈与には生存給付金のついた生命保険を活用することができます。 例:毎年、生存給付金を受け取れる生命保険を契約し、給付金の受取人を子どもや孫などの贈与相手に設定することで、毎年一定額を生前贈与することができます。給付金額を110万円以下にすることで非課税となり、節税効果も得られます。
まとめ
いかがでしたか?
生前贈与を行う場合、家族でよく話し合い、自分たちに合った適切な方法で財産の受け渡しをすることが大切です。
適切な贈与方法を選択したり生命保険を上手に活用したりするために、プロに相談してみてはいかがでしょうか。